睡眠時無呼吸症候群の最新治療と対策が「きょうの健康」で紹介!(まとめ)
2025年5月23日再放送の「きょうの健康・“快眠”新生活 「睡眠時無呼吸症候群 働き盛りの睡眠トラブル」
で「睡眠時無呼吸症候群の進歩する治療法」が紹介されました。
解説者は奈良県立医科大学教授山内 基雄(やまうちもとお)先生です。
朝すっきり起きられない、日中に強い眠気がある、大きないびきをかく…そんな症状、実は“睡眠時無呼吸症候群”かもしれません。
心筋梗塞や脳卒中リスクも高まるこの病気は、働き盛り世代に多く、放置は禁物。
今回は治療法の基本から、2021年に保険適用となった最新治療「舌下神経電気刺激療法」まで、最新情報を簡単にまとめます。
この記事の目次
◆ 睡眠時無呼吸症候群とは?
・寝ている間に呼吸が止まる病気
・心臓病や高血圧、脳卒中リスクが上がる
・早期発見・治療が重要
◆こんな症状があったら要注意!(解説付き)
睡眠時無呼吸症候群は、ただ「眠りが浅くなる」だけでなく、心臓や血圧に深刻な負担をかける病気です。
次のような症状がある場合、専門医の受診を検討しましょう。
● 大きないびきをよくかく
→ いびきは「気道(空気の通り道)が狭くなっている」サイン。狭い気道を空気が通るときに振動し、大きないびきとなります。
これは無呼吸の前段階であることが多いです。
● 日中に強い眠気やけん怠感がある
→ 無呼吸により何度も目が覚め、深い眠り(ノンレム睡眠)がとれなくなるため、睡眠時間が足りていても「熟睡できていない状態」に。
集中力や判断力の低下にもつながります。
● 夜中にトイレに起きることが多い
→ 無呼吸状態では心臓に強い負荷がかかるため、体液を減らして心臓の負荷を軽減するために利尿ホルモンが分泌されます。
そのため、夜間頻尿が増えるのです。
● 朝起きたときに頭痛がある
→ 無呼吸により酸素が不足(低酸素状態)になると、脳の血管が広がって血流が変化し、頭痛を引き起こしやすくなります。
● 高血圧で薬を飲んでも下がりにくい
→ 通常、睡眠中は血圧が自然に下がりますが、無呼吸によって繰り返し血圧が急上昇するため、全体として高血圧が持続。薬が効きにくくなります。
⚠ 上記のうち 複数当てはまる方 は、特に注意が必要です。
◆睡眠時無呼吸症候群になりやすい人(特徴と理由)
この病気には特定の「なりやすい体質・生活習慣」があります。
以下の特徴を持つ方は、発症リスクが高いため、症状がなくても予防意識を持ちましょう。
● 肥満・メタボ体型
→ 首回りや喉の脂肪が気道を圧迫しやすく、空気の通り道が狭くなるため無呼吸のリスクが高まります。
● 妊娠中の女性
→ 妊娠により体重が増え、またホルモンの影響で鼻づまりやむくみが起こり、
気道が狭くなることがあります。
● 顎が小さい(小顎症)
→ 下顎が小さいと、舌や喉の構造が気道をふさぎやすくなり、呼吸が止まりやすい形状となります。
● 鼻づまりがある人
→ 鼻呼吸が難しいと、口呼吸が増えて舌が後ろに落ち込みやすくなり、気道閉塞の原因になります。
● 寝る前にお酒を飲む習慣がある人
→ アルコールには筋肉を緩める作用があり、喉の筋肉もゆるんで気道が閉じやすくなります。また、いびきも増加します。
● 閉経後の女性
→ 女性ホルモンには気道を広げる作用がありますが、閉経によりその作用が弱まり、男性と同様に無呼吸のリスクが高まります。
このように、症状とリスク要因には明確な医学的な理由があります。
どれも「たまたま起こる」ものではなく、体の変化や生活習慣に深く関係しています。
気になる症状があれば早めのチェックが何より大切です。
◆治療の基本は生活習慣の改善
・睡眠時間と姿勢の見直し
・減量、禁酒、鼻づまりの対策など
◆主な治療法と選び方
◉マウスピース療法
軽症〜中等症向け
下顎を前に出す設計で気道を広げる
◉CPAP(シーパップ)療法
中等症〜重症向け
鼻マスクで圧のかかった空気を送り込み、気道を確保
日中の眠気や高血圧改善、発作リスク減少などの効果あり
◉舌下神経電気刺激療法(2021年保険適用)
CPAPが使えない人向けの最新選択肢
鎖骨下とあごの2箇所を切開し、舌に電気刺激を与えることで気道を確保
パルスジェネレーターは11年使用可能
◆まとめ
睡眠時無呼吸症候群は、いびきや日中の眠気といった一見よくある症状の裏に隠れている、重大な健康リスクです。
放置すれば心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気の引き金になる可能性もあります。
とくに働き盛りの世代や、肥満・閉経後の女性などは発症リスクが高く、注意が必要です。
治療はまず生活習慣の見直しから始まり、マウスピースやCPAPといった装置による治療、さらに近年保険適用となった舌下神経電気刺激療法と、選択肢は広がっています。
症状やライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる治療を選ぶことが大切です。
「いびきなんて誰でもかく」と軽視せず、気になる症状が複数あれば専門医の診察を受けましょう。
最新治療は限られた医療機関で行われているため、専門医の紹介がカギになります。
正しい治療と対策で、質の高い眠りを取り戻し、日中のパフォーマンスや将来の健康を守ることができます。

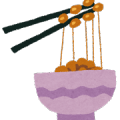








最近のコメント